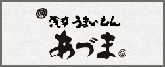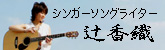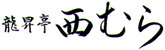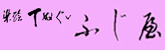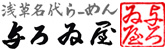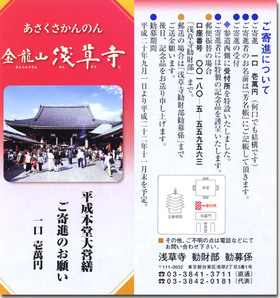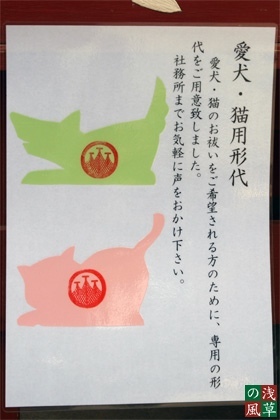2009.0617撮影。
伝法院通りに面した門から入った境内。左がお堂。右が水子地蔵尊。
鎮護堂は、明治16年(1883)浅草寺の第17世貫首が、夢のお告げにより境内に棲む狸を伝法院の守護としてまつったもの。赤門、水子地蔵尊、加頭地蔵尊もあります。入口は伝法院通り西側にあり、お狸さまと呼ばれ親しまれています。
鎮護堂の前の記事はこちらです。
鎮護堂内部の記事はこちらです。
鎮護堂の紹介ページ(伝法院通り商店街サイト)はこちらです。
浅草寺の鎮護堂ページはこちらです。
浅草検索
- 「浅草の風」内検索
- 浅草観光主要サイト横断検索
カテゴリー
- 00a はじめにお読みください (1)
- 00b お知らせ・ごあいさつ (61)
- 00c 浅草の通り地図 (21)
- 00d 浅草寺・浅草神社 (2275)
- 00f 町のようす (3739)
- 00g 隅田川・隅田公園 (181)
- 00h 食べる・飲む (267)
- 00i 買う (34)
- 00j その他の神社・仏閣・宗教施設 (113)
- 00k 浅草寺子屋 (7)
- 00m 浅草の写真と俳句 (40)
- 00n 浅草の猫たち (290)
- 00o 紹介 (294)
- 01月 亡者送り(温座秘法陀羅尼会) (2)
- 01月 待乳山聖天 大根まつり (8)
- 01月 新春浅草歌舞伎 (13)
- 01月 江戸消防記念会はしご乗り (3)
- 01月 浅草三団体合同新年会 (3)
- 01月 除夜の鐘、初詣 (64)
- 02月 浅草の節分 (39)
- 02月 針供養 (5)
- 02月 隅田公園梅まつり (4)
- 03月 大平和塔戦災殉難者法要 (4)
- 03月 東京マラソン (22)
- 03月 江戸流しびな (8)
- 03月 浅草寺本尊示現会 (33)
- 04月 投扇興の集い (12)
- 04月 早慶レガッタ安全祈願パレード (2)
- 04月 泣き相撲 (22)
- 04月 浅草流鏑馬 (11)
- 04月 浅草神社花塚慰霊祭 (1)
- 04月 花まつり・白鷺の舞 (11)
- 04月 観音裏一葉桜まつり (3)
- 04月 誓教寺北斎忌 (1)
- 05、6月 植木市 (17)
- 05月 三社祭 (110)
- 05月 江戸消防慰霊祭(弥生祭) (1)
- 05月 福寿 宝の舞 (2)
- 06月 夏越大祓 (1)
- 06月 長國寺あじさい祭 (1)
- 07月 下町七夕まつり (23)
- 07月 入谷朝顔まつり (12)
- 07月 四万六千日・ほおずき市 (27)
- 07月 浅草寺打ち水大作戦 (1)
- 07月 観音裏みちびきまつり (8)
- 07月 隅田川花火大会 (9)
- 08月 万霊灯供養会 (6)
- 08月 千束通りスーパーROCKよさこい祭 (3)
- 08月 夏の夜まつり灯ろう流し (17)
- 08月 浅草サンバカーニバル (33)
- 08月 町会盆踊り・子ども大会 (1)
- 09月 南魚沼らいす・ぬーぼー (2)
- 09月 浅草燈籠会 (8)
- 09月 浅草阿波踊り (4)
- 10、11月 浅草菊花展 (35)
- 10月 写経供養会 (1)
- 10月 浅草奥山こども歌舞伎まつり (9)
- 10月 菊供養会・金龍の舞 (28)
- 11月 したまちコメディ映画祭 (2)
- 11月 国際通りビートフェスティバル (11)
- 11月 山形県村山市観光物産展 (8)
- 11月 東京時代まつり・白鷺の舞 (41)
- 11月 浅草酉の市 (29)
- 12月 たぬきまつり (7)
- 12月 冬の一葉桜イルミネーション (2)
- 12月 歳の市(羽子板市) (45)
- 12月 花川戸はきだおれ市 (5)
- 13 隣接地域のイベント (1)
- 19 浅草の基本情報 (18)
- 200709 F1レッドブル入賞祈願 (10)
- 200810宝蔵門大草鞋掛け替え (4)
- 2008浅草寺本堂落慶50年大観光祭 (164)
- 20 プロフィール (1)
- つくばエクスプレス浅草駅 (4)
- アミューズ ミュージアム (18)
- 大東京和おどり (4)
- 循環バス「めぐりん」 (8)
- 浅草に江戸芝居小屋をつくる運動 (45)
- 浅草の隣接地域 (1)
- 浅草名所七福神巡り (4)
- 浅草国際通りビートフェスティバル (4)
- 浅草神社子供教化活動 (7)
- 管理人、風の体調について (21)
- 隅田川、水上バスの旅 (10)
- 雪の浅草 (38)
カウンター
- 2007.04.15より
合計:
昨日:
今日: