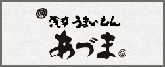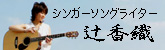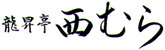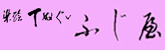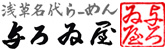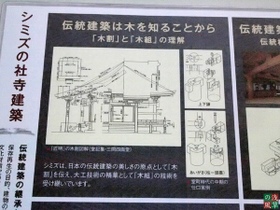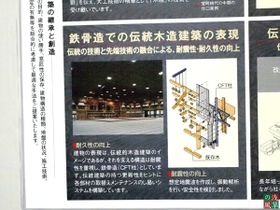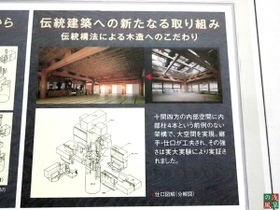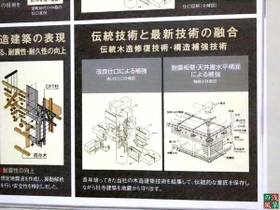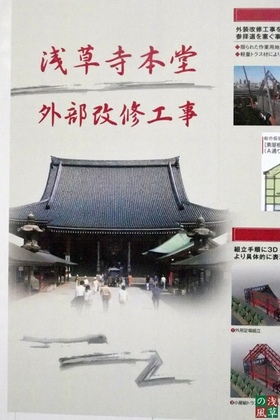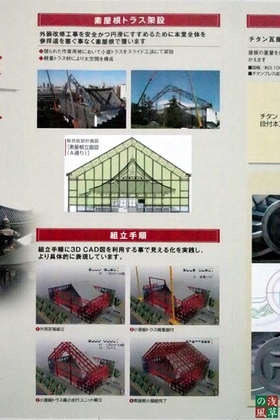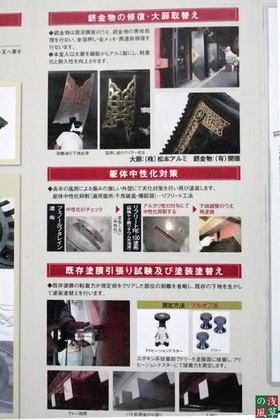2009.11.09撮影。
ご心配をおかけしています。浅草の風です。
肺癌の転移で治療のために入院しましたが、検査を終えて一度退院してきました。まもなく本格治療のために再び入院します。小さなカメラを持って、雷門から本堂まで写真を撮りながら往復しただけでしたが、すっかり疲れてしまいました。体力が無くなったものです。
二天門は、元和4年(1618)に建立。当初は境内にあった東照宮の随身門でした。現在は保存修理中です。
工事前の二天門の記事はこちらです。
浅草寺のホームページはこちらです。
浅草検索
- 「浅草の風」内検索
- 浅草観光主要サイト横断検索
カテゴリー
- 00a はじめにお読みください (1)
- 00b お知らせ・ごあいさつ (61)
- 00c 浅草の通り地図 (21)
- 00d 浅草寺・浅草神社 (2275)
- 00f 町のようす (3739)
- 00g 隅田川・隅田公園 (181)
- 00h 食べる・飲む (267)
- 00i 買う (34)
- 00j その他の神社・仏閣・宗教施設 (113)
- 00k 浅草寺子屋 (7)
- 00m 浅草の写真と俳句 (40)
- 00n 浅草の猫たち (290)
- 00o 紹介 (294)
- 01月 亡者送り(温座秘法陀羅尼会) (2)
- 01月 待乳山聖天 大根まつり (8)
- 01月 新春浅草歌舞伎 (13)
- 01月 江戸消防記念会はしご乗り (3)
- 01月 浅草三団体合同新年会 (3)
- 01月 除夜の鐘、初詣 (64)
- 02月 浅草の節分 (39)
- 02月 針供養 (5)
- 02月 隅田公園梅まつり (4)
- 03月 大平和塔戦災殉難者法要 (4)
- 03月 東京マラソン (22)
- 03月 江戸流しびな (8)
- 03月 浅草寺本尊示現会 (33)
- 04月 投扇興の集い (12)
- 04月 早慶レガッタ安全祈願パレード (2)
- 04月 泣き相撲 (22)
- 04月 浅草流鏑馬 (11)
- 04月 浅草神社花塚慰霊祭 (1)
- 04月 花まつり・白鷺の舞 (11)
- 04月 観音裏一葉桜まつり (3)
- 04月 誓教寺北斎忌 (1)
- 05、6月 植木市 (17)
- 05月 三社祭 (110)
- 05月 江戸消防慰霊祭(弥生祭) (1)
- 05月 福寿 宝の舞 (2)
- 06月 夏越大祓 (1)
- 06月 長國寺あじさい祭 (1)
- 07月 下町七夕まつり (23)
- 07月 入谷朝顔まつり (12)
- 07月 四万六千日・ほおずき市 (27)
- 07月 浅草寺打ち水大作戦 (1)
- 07月 観音裏みちびきまつり (8)
- 07月 隅田川花火大会 (9)
- 08月 万霊灯供養会 (6)
- 08月 千束通りスーパーROCKよさこい祭 (3)
- 08月 夏の夜まつり灯ろう流し (17)
- 08月 浅草サンバカーニバル (33)
- 08月 町会盆踊り・子ども大会 (1)
- 09月 南魚沼らいす・ぬーぼー (2)
- 09月 浅草燈籠会 (8)
- 09月 浅草阿波踊り (4)
- 10、11月 浅草菊花展 (35)
- 10月 写経供養会 (1)
- 10月 浅草奥山こども歌舞伎まつり (9)
- 10月 菊供養会・金龍の舞 (28)
- 11月 したまちコメディ映画祭 (2)
- 11月 国際通りビートフェスティバル (11)
- 11月 山形県村山市観光物産展 (8)
- 11月 東京時代まつり・白鷺の舞 (41)
- 11月 浅草酉の市 (29)
- 12月 たぬきまつり (7)
- 12月 冬の一葉桜イルミネーション (2)
- 12月 歳の市(羽子板市) (45)
- 12月 花川戸はきだおれ市 (5)
- 13 隣接地域のイベント (1)
- 19 浅草の基本情報 (18)
- 200709 F1レッドブル入賞祈願 (10)
- 200810宝蔵門大草鞋掛け替え (4)
- 2008浅草寺本堂落慶50年大観光祭 (164)
- 20 プロフィール (1)
- つくばエクスプレス浅草駅 (4)
- アミューズ ミュージアム (18)
- 大東京和おどり (4)
- 循環バス「めぐりん」 (8)
- 浅草に江戸芝居小屋をつくる運動 (45)
- 浅草の隣接地域 (1)
- 浅草名所七福神巡り (4)
- 浅草国際通りビートフェスティバル (4)
- 浅草神社子供教化活動 (7)
- 管理人、風の体調について (21)
- 隅田川、水上バスの旅 (10)
- 雪の浅草 (38)
カウンター
- 2007.04.15より
合計:
昨日:
今日: